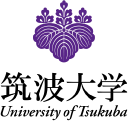2025年度の
プロジェクト採択実績
戸田PJ
- プロジェクト代表者名
- 戸田 浩史
- 所属
- 国際統合睡眠医科学研究機構 助教
- 課題名
- 新規抗菌ペプチドの発展とその薬剤耐性菌への応用開発
プロジェクトの概要
薬剤耐性細菌は、世界各国において、公衆衛生や医療に深刻な脅威を与え、2019年には約127万人が耐性菌で死亡、約500万人が関連死とされている。新規抗菌薬が開発されても耐性菌が発生してしまう問題に対し、効果的な打開策はこれまで存在しない。耐性菌抗菌薬の市場は世界で約12兆円と試算され、今後もCAGR5%の増加見込みである。この課題に対し、我々は、幅広い薬剤耐性菌に対して高い効果を示し、且つ、耐性菌の発生を抑制できる可能性を持つ抗菌ペプチド「Nemuri」を発見した。本事業では、Nemuriを用いた抗菌薬の改良、製造、販売を行う事業を通じて、耐性菌問題を解決し、100万人以上の命を救うことを目指す。
三浦PJ
- プロジェクト代表者名
- 三浦 謙治
- 所属
- 生命環境系 教授
- 課題名
- 植物による高価値タンパク質の低コスト生産プラットフォームの事業化
プロジェクトの概要
特定の分子や細胞に選択的に作用し、副作用が少ないバイオ医薬品は、2024年時点で世界市場規模が約4兆4千億円とされ、今後も年平均成長率(CAGR)7.56%で拡大が見込まれている。しかし、これらの医薬品は分子構造が複雑で、生物由来の生産が必要なため、生産コストが高く、日本では一人当たり年間50万円以上の医療費負担が発生するなどの課題がある。本事業では、植物を利用した高価値タンパク質を安価に生産するプラットフォームの開発・事業化を目指す。これにより、製薬企業に対して高価値なタンパク質を低コストで提供し、世界中の患者に副作用の少ない医薬品を届けることで、健康な社会の実現に貢献する。
林PJ
- プロジェクト代表者名
- 林 利有樹
- 所属
- 農学学位プログラム博士後期課程 1年
- 課題名
- 海藻残渣から得る藻類繊維と藻類繊維由来の透明化エコマテリアル「Mowtex」の事業化
プロジェクトの概要
陸上利用と競合しない資源として、水圏で得られる海藻などのブルーカーボンの活用拡大が今後見込まれるが、 同時に生じる海藻残渣の処理が課題である。そこで申請者は海藻残渣から繊維分を単離、また、生分解性と透明性を持つ藻類由来の透明化材料「Mowtex」を開発した。 本事業では藻類繊維及びMowtexの用途開発と顧客要求仕様の実現に向けた製品開発を進め、26年を目標にMowtex製品の市場投入を目指す。また、海藻残渣活用のエコシステムを組み込んだビジネスモデルを確立し、藻類由来の機能的な材料活用を示すことでブルーカーボン活用社会を創出、拡大する水圏の活用も含んだカーボンニュートラルを実現する。
川崎PJ
- プロジェクト代表者名
- 川崎 真弘
- 所属
- システム情報系 准教授
- 課題名
- 食品摂取時の飽きやすさ予測モデルを用いた商品開発支援
プロジェクトの概要
本テーマでは、食品の「官能特性」と脳波データを統合し、消費者が“一回分”を食べ進める中で感じる「飽きやすさ」を科学的に予測するモデルを基盤としたビジネスを構想している。本モデルは、従来の官能評価だけでは捉えきれなかった「飽きやすさ」を定量化し、企業の商品開発支援や試作品評価、飽きやすさ比較(自社/他社製品)に応用できる。これにより、食品業界における開発プロセスの効率化と、消費者体験・リピート購入率の向上を目指す。また本技術は、健康志向市場への展開も期待され、社会における食体験の質向上に貢献する可能性がある。
櫛田PJ
- プロジェクト代表者名
- 櫛田 創
- 所属
- 数理物質系 助教
- 課題名
- 生分解チクソトロピー低分子溶媒に根ざした塗装・接着剤応用
プロジェクトの概要
「爪を傷つけず強力に接着でき、かつ剥がしやすい」次世代型ネイル接着剤の事業化を目指す。従来のネイル接着剤は、強力なものは除去時に爪を損傷し、弱いものは日常生活で剥がれやすいという課題がある。本技術は、申請者らが独自に開発した新原理に基づく分子性チクソトロピー材料と、アミノ酸の光重合・光分解機能を組み合わせることで、塗布・接着・除去を自在に制御できる。ファッションがもたらす人々の幸福の最大化に寄与しつつ、化学技術の社会実装を通じてその価値の裾野を広げ、サイエンスへの関心が自然と高まる社会の実現を目指す。さらに、医療や自動車整備用途など、非破壊性と可逆性が求められる他分野への展開も視野に入れる。
矢島PJ
- プロジェクト代表者名
- 矢島 秀伸
- 所属
- 計算科学研究センター 准教授
- 課題名
- 革新的な光輸送シミュレーションによる次世代脳出血モニタリング
プロジェクトの概要
本事業は、光輸送シミュレーションとAI技術により非侵襲かつ迅速な病気モニタリングシステムを提供する事業を行う。本技術は出血やがん等複数の用途が可能だが、主に頭部外傷モニタリングを想定して事業を検討中である。頭部外傷は日本で年間約30万人と推定され、その中で硬膜下血腫は72時間まで注意が必要とされる。しかし、診断はX線CTなどを持つ大規模な病院に限られており、簡易かつ高精度な診断が求められている。本技術は簡易な装置で血腫有無を診断することができるため、経過観察の診断精度を向上させ脳出血の進行をリアルタイムに把握することが可能となる。また、その簡易性により地方と都市の医療格差の是正にも貢献する。そのために、スーパーコンピュータを用いて革新的な光輸送シミュレーションを行い、AI技術を駆使してオンラインによる迅速な診断システムを開発する。